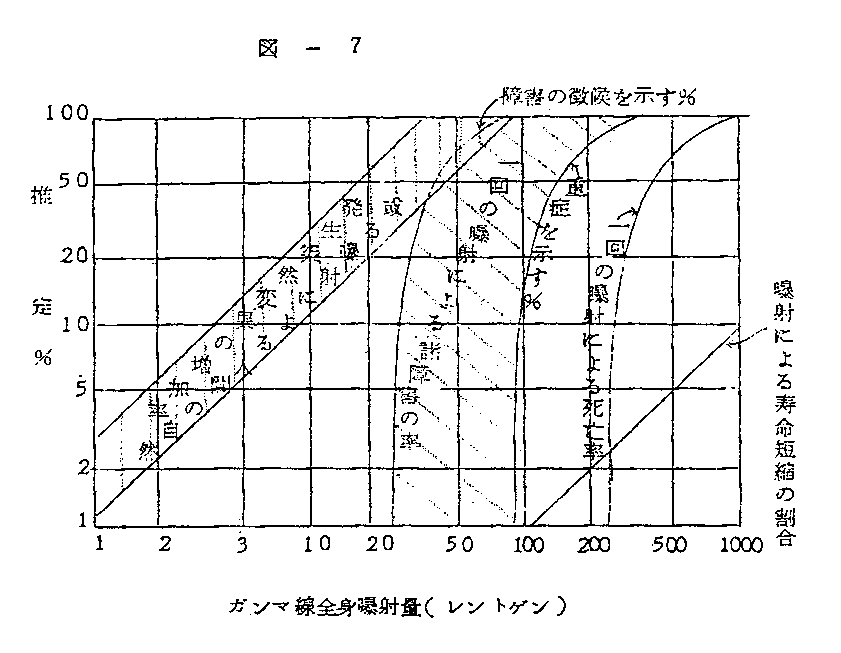
土地よりの立退及ぴ主居の制限については土地に沈着した放射性放出物により人体が受 ける被曝線量により評価されるべきである。
先ず汚染された土地よりのγ線量を見ると、線量は一様の汚染度 Sa c/m2 の土地 (平面とする)の上の人体が高さhにおけるγ線量率はγ線の平均エネルギーを
γ
Eav とすれば (13)
γ ∞ e-y
R = 1.07 × 102 (μm) tissne × Eav Sa 〔∫ ―― dy + e-μh 〕rad / hr
μh y
となる。
但し(μm) tissue はEγ 0.1 〜 2Mev のハンイでは0.03cm2/g とする。
h = 1m とすれば、計算より
∞ e-y
〔∫ ―― dy + e-μh 〕≒ 5.0
μh y
とすることが出来るから
γ
E = 0.7 Mev とすれば
av
土地平面上 1m の高さの人体の受けるγ線量率は
R = 1.07 × 102 × 0.03 × 0.7 × 5.0 × Sa = 11.2 × Sa rad/hr
今 Sa c/m2 を事故後24時間後の沈着濃度とし、放射性物質の崩壊は t-m の法則によるとすれば、事故後2時間目の汚染度は
2
Sa 2h = Sa ( ―― )-m
24
従つて2時間目より14時間目までに受ける線量は
2〜14 14 t
D = 11.2 × Sa ∫ ( ―― )-m dt rad
S 2 24
Total F.P のときは m=0.2 と想定するから、
2〜14 14 t 2.40.2
D = 11.2 × Sa ∫ ( ―― )-m dt = 11.2 Sa × ―― (140.8 - 20.8 )
TFP 2 24 0.8
1.88
= Sa × 11.2 × ――― ( 140.8 - 20.8 ) = Sa × 11.2
0.8
1.88
× ――― ( 8.248 - 1.741 )
0.8
1.88
= Sa × 11.2 × ――― × 6.507 = 173 Sa
0.8
Volatile F.P. のときは m = 0.8 とするから
2〜14 14 t 12.7
D = 11.2 Sa ∫ ( ―― )-0.8 dt = Sa × 11.2 × ――― × 0.547 = 390 Sa
V.F.P. 2 24 0.2
もし放出後6時間目に放射能雲が飛来したとすれば、
Total F.P. のとき
6〜18 18 t
D = 11.2 Sa ∫ ( ―― )-0.2 dt = 155 Sa
TFP 6 24
Volatile F.P. のときは
6〜18 18 t
D = 11.2 Sa ∫ ( ―― )-0.8 dt = 250 Sa
VFP 6 24
Volatile F.P. の減衰を3ヶ月まで-0.8が有効と想定すれば、3ヶ月間に受け る線量は
Total F.P. では
〜3ヶ月 2160 t
D = 11.2 Sa ∫ ( ―― )-0.2 dt
TFP 2 24
= 12200 Sa rad
Total F.P. では
〜3ヶ月 2160 t
D = 11.2 Sa ∫ ( ―― )-0.8 dt
VFP 2 24
= 2580 Sa rad
となる。
従つて、1日目より3ヶ月までの、1日の平均線量率は
Total F.P. では 12200 Sa ÷ 90 = 135 Sa rad/日
Volatile F.P. では 2580 Sa ÷ 90 = 29 Sa rad/日
となる。
今、被曝後12時間以内に12rad以上の被曝を受ける地域をA級の緊急立退地域と すればその限界は
| 揮発性放出 | 1時間後の被曝地では | 12/390 = 0.03 C/m2 |
| 〃 | 6 〃 〃 | 12/250 = 0.05 C/m2 |
| 全放出 | 1 〃 〃 | 12/173 = 0.07 C/m2 |
| 〃 | 6 〃 〃 | 12/155 = 0.08 C/m2 |
次に被曝後3ヶ月以内に25rad 以上を受けるおそれのある区域をB級の立退地域と
すれば、これに当る土地汚染の限界は
全放出物の汚染では
25 ÷ 12200 = 2 × 10-3 C/m2
揮発性放出物による汚染では
25 ÷ 2580 = 1 × 10-2 C/m2
である。
地表面の汚染より受ける線量は自然の物理的減衰、雨、風等による地表面よりの移動等 の原因により、次第に減弱するから、一定の期間の後には汚染された地上において単に居 住する程度の事はさしつかえなくなるであろう。とくに都市においては食物等をたの汚染 のない地域より移入し、又飲料水を適当に浄化する施設があるとすれば、単なる地面の若 干の汚染により住居の永久制限をすることは甚だしく不経済であり、且つ、大きな社会 的負担となるから、住居のみを許し得る限界、とくに一定の期間の後に再び住居してよ い限界というものをきめる必要がある。このような限界をC級の住居制限限界とすれば、 これをどのような基準で行うかが問題となる。
Volatile F.P. の自然減衰は比較的早く
はじめの1ヶ月間の平均日線量率は 53 Sa rad/日
3ヶ月間の平均日線量率は 29 Sa rad/日 である。
従つて、1ヶ月以後毎日の線量として、0.033rad(年間12rad、13週間 3rad) を許される線量とすれば1ヶ月後に居住が許されると考えられる地域は、 0.033 ÷ 29 ≒ 1.1 × 10-3 C/m2 である。(長期の平均日線量率は明らかに 30 Sa rad/日より小となる)
Total F.P. による汚染の場合は、自然減衰がかなりゆつくりであるから 住居許容限界基準はより severe にする必要がある。
1ヶ月の平均日線量率は
〜1ヶ月 26.3 × Sa( 192.8 - 1.74 )
D = ――――――――――――――― = 170 Sa rad/日
/30日 30
3ヶ月の平均日線量率は
〜3ヶ月 26.3 × Sa( 464.5 - 1.74 ) 12200
D = ――――――――――――――― = ―――― Sa = 135 Sa rad/日
/90 90 90
1ヵ年間の平均日線量率は
〜1ヵ年 26.3 × Sa( 1424 - 1.74 ) 37000
D = ―――――――――――――― = ―――― Sa = 100 Sa rad/日
/365 365 365
従つて、事故後1ヶ月たつて、居住を認めるとして、その後日平均線量率が 0.0135 rad をこえない(即ち年間5radをこえない)地域を居住許容地域とすれば、その ような地域は表面汚染として
0.0135 ÷ 135 = 10-4 C/m2 より低い地域とすれば間違いない。
以上を総括して、C級の地域として、1ヶ月後に居住を容許し得る地域とし
揮発性放出物の汚染では 10-3 C/m2 以下 全放出物の汚染では 10-4 C/m2 以下とすることが妥当と考えられる。
しかし、日本の特異性と計算の便宜とを考慮して、附録(E) にある農耕禁止の基準 6×10-4 4×10-5 にそれぞれ合わせることにした。
但し、気象条件などによる地表の除染効果を大きく認め得るとすればこの限界はさらに中に入り得ると考えられる。
| D | 25 〜 100r | {90日間の医学的検査及び観察を必要。 |
| E | 25r 以下 | 障害はない。 |
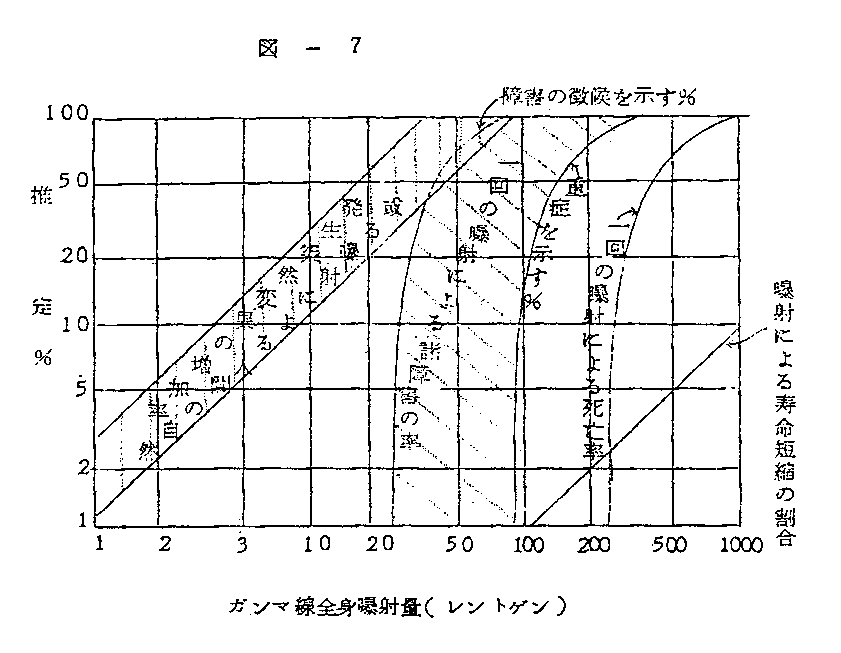
以上の想定の上、治療及び検査の内容を具体的にあてはめれば、それらの計算は可能となる。
2.次に、事故後に放出された分裂生成物の煙霧に曝された場合、人体の受ける線量は別の 計算により第B表の如くなる。この表のCの値を種々変えると、全身その他の臓器の被曝 線量が分る。これにより、1で述べた全身一時被曝による障害と同程度の障害を与えると 考えられるCの価を決定すれば、人体に対する災害の評価を行いうる。
この場合、判定の基準を主として被曝後1日間に受ける線量におき、それ以後の被曝量 は参考とすることにした。その理由は、例えば骨が1年間に何rad受ければ死亡するが、 或いは何radで治療を要する障害が現れるかということは分つていないからである。勿論 1日目の被曝にしても、各臓器の被曝が占める割合を決定的にいうのは困難であるが、長 期のことを考えるよりは容易であろう。
また、白血病、骨腫瘍、白内障等が、放射線被曝によつて後年、発生率が高くなるで あろうことは想像出来る。然し、被曝線量と発生率の関係は決定的なことはいえない。
従つて、ここではこれらの考え得る晩発症については、一応除外した。然し、これらの 補償については別に考慮する必要があろう。
500c-sec/m3の被曝では a) 粒度小で放出後1時間目なら、全身 に715rad、肺に220rad、消化管に27.5rad、甲状腺には29.150 radを第1日に受け、骨は1年間に5.885radを1年間に受けることになる。
この時の甲状腺の被曝は、放射能症の発生やそれによる死亡には、決定的な寄与を なすものとは考えられず、また、肺、消化管の被曝量は比較的少い。従つて全身被 曝量のみを注目してよかろう。
| 700r | 相当量=550 | c-sec/m3 |
| 200r | 〃 =150 | 〃 |
| 100r | 〃 = 80 | 〃 |
b) 粒度大なる場合は、消化管の被曝量が、a)に比して約12倍となる。これは 全身状態に影響するだろうが、550 c-sec/m3 の濃度で消化管は 330 radを受ける。消化管の被曝を全身被曝と等価とみると、700rに相 当するのは400c-sec/m3位という計算になるが、両者にはそれ程大きい 差は実際には存在しないだろう。
また、検査のみ実施する範囲は、安全限界を越える被曝で、100〜相当濃度 以下にすべきであろう。
放出後6時間目の被曝では、それぞれ1時間目に比し、約2倍の濃度となるだろう。
a)粒度小
上と同様にして推定するが、肺及び消化管の被曝を考慮して、全身被曝に加算 した。
| 700〜 | =800 | c-sec/m3 |
| 200〜 | =200 | 〃 |
| 100〜 | =100 | c-sec |
a)粒度大 同様にして
| 700r | =250 | c-sec/m3 |
| 200r | =80 | 〃 |
| 100r | =40 | 〃 |
a)で最も問題となるのは、被曝后1年間に受ける骨の線量の判定であろう。従来も 長年月(20年以上)のRa障害者に骨腫瘍の発生をみた報告もあるが、被曝後、初期 における見通しは立てられない。また、投書の1年間に大量の被曝を骨が受ければ、造 血障害も起り得ると思われるが、治療費の計算を行い得る程のデーターはないため除外 した。
以上の数値は大部分推量である。出来るだけ既存のデーターを参考にしたが、これは あく迄も、災害評価のために引いたラインであると考えていただきたい。